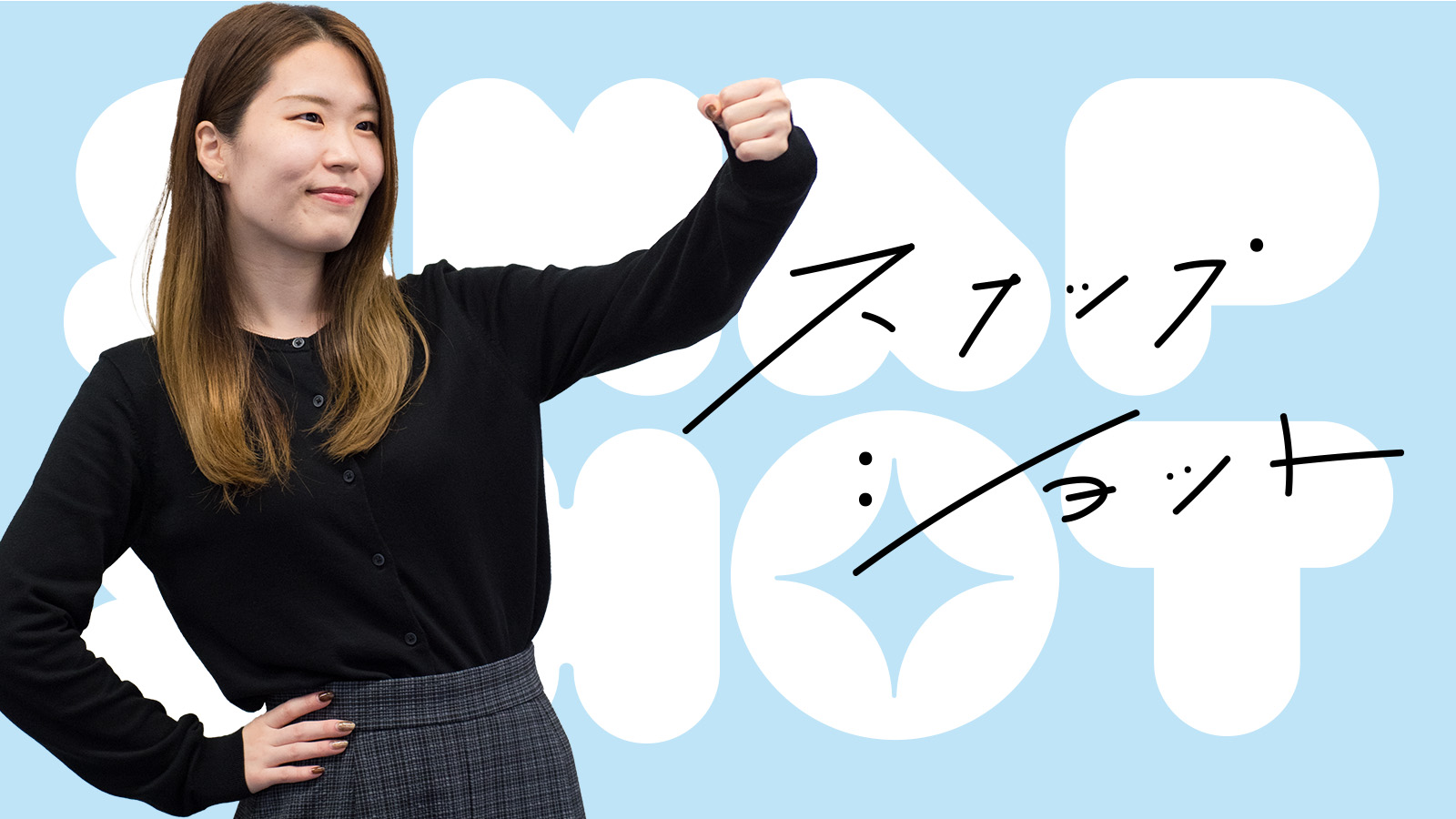現場が変われば、設備が変わる
設備が変われば、自分が変わる
浜岸 太郎
2019年入社
保全エンジニア
PROFILE
プロフィール
福井県出身。前職はスーパーマーケットで勤務。しかし、手に職をつけたいと思い転職することを決意。転職サイトで仕事を探しているときに、日研と出会う。現在は大手自動車メーカーに出向し、設計や開発の仕事に携わる。
浜岸さんのキャリア
製造エンジニア
自動車バッテリー工場 2年
仕事内容:部品の組立、検査、梱包作業
関西テクノセンターで保全研修 1.5ヵ月
保全の基礎知識
保全エンジニア
アルミ製造工場 2年半
仕事内容:機械や設備のメンテナンス
テクノセンターでスキルアップ研修 1.5ヵ月
自動化システムや設備を使ったスキルアップ
保全エンジニア 現在
大手自動車メーカーに出向
仕事内容:設計や開発
STORY 01
1年目 製造エンジニア
設備における
一連の流れを把握する
仕事について
以前はスーパーマーケットで品出しや商品の発注、売り上げの管理をする仕事をしていました。しかし、入社から2年が経った頃から、「何か手に職をつけたい」と思うようになり、転職サイトを見ていたときに出会ったのが、日研トータルソーシングでした。今までやってきたこととは全く異なる理系チックな「保全」という仕事に興味を抱いて入社を決めました。入社してすぐは京都にある自動車用のバッテリー工場に配属されました。
学んだこと
主に部品の組立、バッテリーの検査、そして梱包といったことをやりました。まずは現場でオペレーター作業をして製造業とはどういうものかというのを知るためですね。ひとつの設備の中で、どういう流れで製品がつくられていくのかを把握することはとても重要です。なぜなら後に経験する保全では、トラブルが発生した際にどこから修理すれば最も生産効率が高いかという優先順位づけが肝になるからです。製造エンジニアとして設備の一連の流れを理解することで、各工程の重要度や修理する作業時間を的確に判断できるようになりました。

STORY 02
3年目 研修
文系の未経験でも
一人前に育てる環境がある
研修について
保全マンとして工場で活躍するために、関西テクノセンターで保全のスタンダード研修を受講し機械や電気に関する基礎知識を学びました。初めて見る工具を扱ったり電気回路を設計したり、最初はついていけるか不安でしたが、講師の方たちは何も知識がない人たちを育てるプロ。文系出身の私でもすんなりと理解できるように説明してくださいました。
学んだこと
お世話になった講師には、技能面だけでなく派遣先に行った時に、どういう風に上司や社員たちと関わっていくべきかという人としてのあり方も教わったので、本当に感謝しています。スキルは時間と経験を積めば自ずと習得できるものですが、人間力は強く意識しないと磨かれていかないもの。テクノセンターでヒューマンスキルを学べたことは、私にとって大きかったです。

STORY 03
3年目 保全エンジニア
すべては準備と段取り
それが尊敬する上司の教え
仕事について
研修を経てからは、アルミ製造工場で主に電気関係の保全をメインで行いました。一言で保全と言っても、設備の故障を直す、図面を書く、設備を動かすためのプログラムを考えるなど、さまざまなことを覚える必要があるので大変だと感じるときもあります。ですが自分が考えたプログラム通りに設備が動いたときには、すごく満足感や達成感を感じられました。
学んだこと
ここでの経験を通じて感じたのは、準備や段取りが大切だということ。何も用意しないで現場に行くのと、予め計画を立てて行くのとでは作業時間が圧倒的に違います。また、準備、実行、振り返りのPDCAを回すことで成長スピードや達成感も変わってきます。もちろん突発的なトラブルが発生した際には急を要するので準備が難しいですが、設備の工程や電気回路などを予習しておくことで対応の質が高まります。これは尊敬する当時の上司の教え。「暇があったら設備を見て勉強してこい」という言葉を、今でも大切にしています。

STORY 04
5年目 研修
ゼロからものを
つくり上げる大変さ
仕事について
次の職場が大手自動車メーカーで生産準備の業務をすることが決まっていたため、出向する前に即戦力として活躍できるよう、自動車や生産準備に特化した研修を受講しました。大手自動車メーカー出身の講師が日研社内にいますので、その方に自動車メーカーの特徴や技術面、安全面に関することを教わりました。こうしたカスタマイズ研修によって実践的な知見を得られるのも日研のよいところだと思います。
学んだこと
生産準備というのは、ゼロから設備を構築し、それを工場に導入していく業務になります。保全という「ものを直す立場」から、「ものをつくり込む立場」に変わることになるのですが、ゼロからものをつくり上げていく大変さを体感できたのは貴重でした。一方で、これまで自分が大切にしていた準備や段取りが生産準備の業務で生かされる実感もあり、自信につながりました。

STORY 05
5年目 保全エンジニア
バーチャルとリアル
双方の視点を持つ
仕事について
大手自動車メーカーで出向という形で勤務しています。そこでは生産準備の業務の中でも、主に産業ロボットのティーチングを担当しています。ティーチングとは、ロボットが正しく挙動するよう、始動のタイミング、動きの順番など細かい動作をプログラミングしていくこと。自動車メーカーは新しい車種が世に出ることになると、それに応じて設備やロボットのプログラムを追加、調整する必要があるんです。
学んだこと
最初はロボットがうまく動かせませんでした。ロボットのちょっとした姿勢の違いひとつでその挙動が変わってしまう繊細なものだからです。あくまで作業はPC上でプログラムを入力していくことですが、リアルな現場での状態も含めて的確に把握することで初めてロボットに命が吹き込まれます。バーチャルとリアルを頭の中でつなぎ合わせる、とても奥が深い仕事です。

CAREER VISION

まだまだ短い期間しか保全を学ぶことができていないので、今後も経験を積んでいく必要があると思っています。そして経験を積んだ後には、テクノセンターの講師となって、自分が学んできたことを人に教えられたらと思っています。また、日研にはさまざまなキャリアを経験できる土壌があります。だから失敗を恐れず、いろんな経験をしてみたいですね。