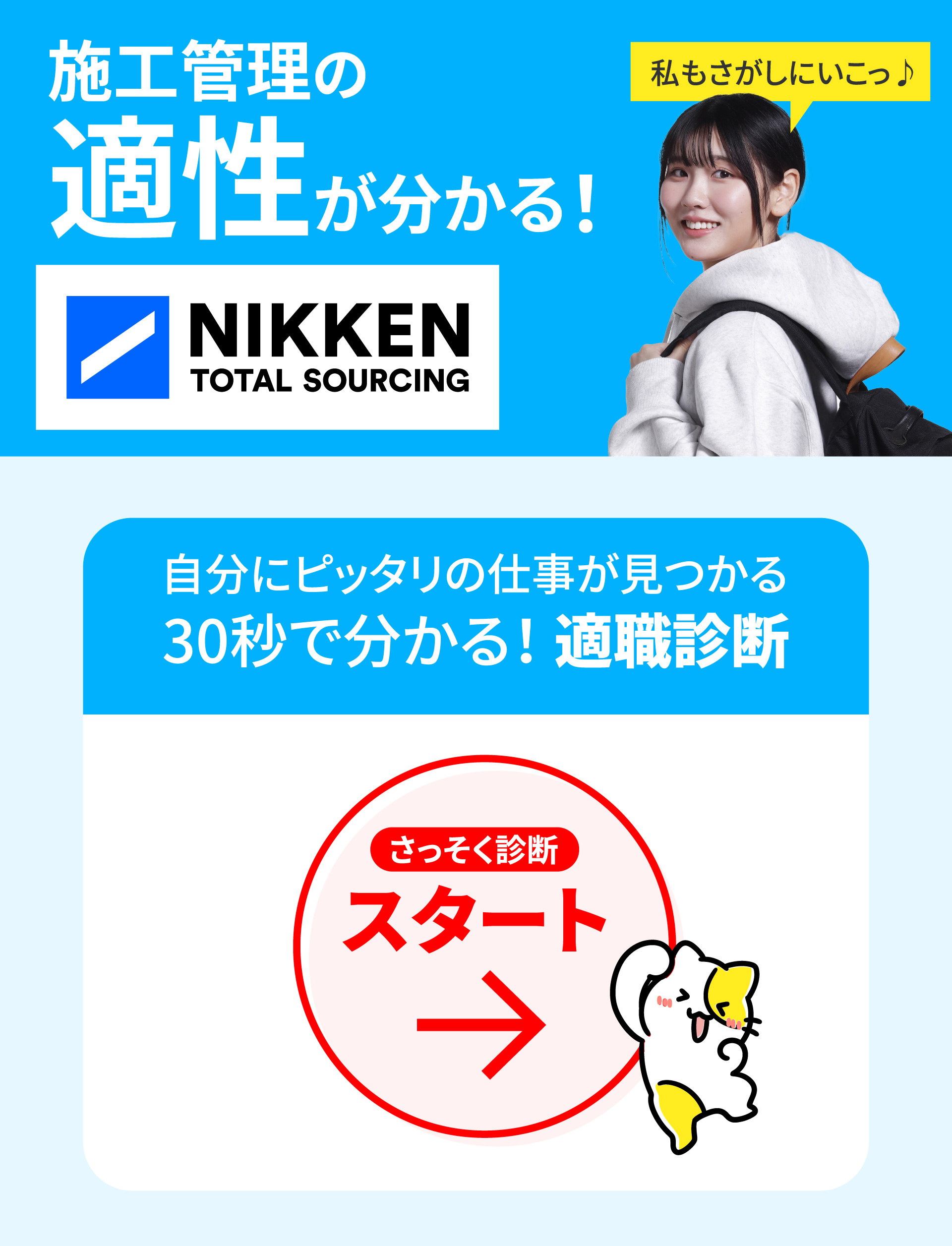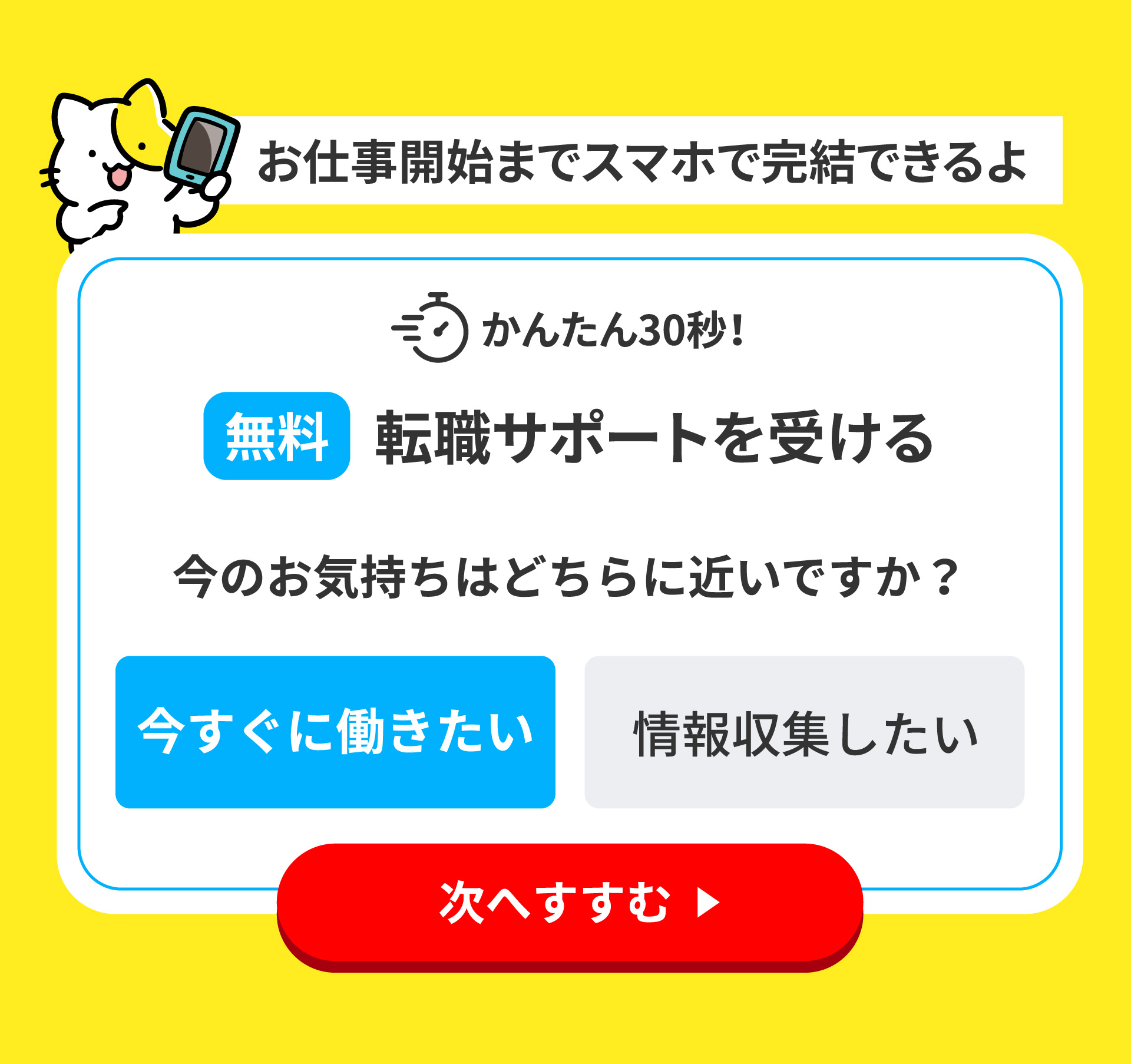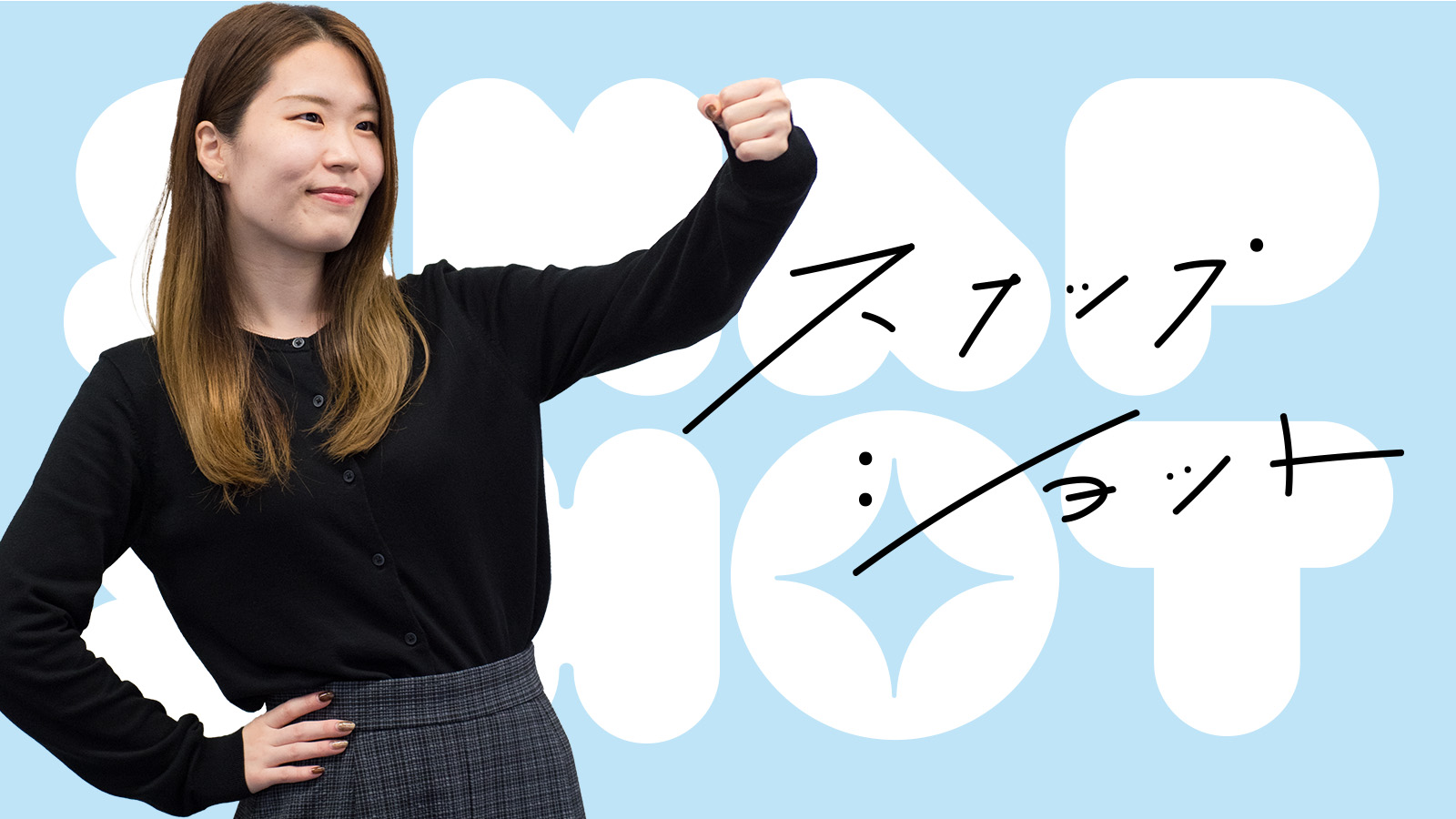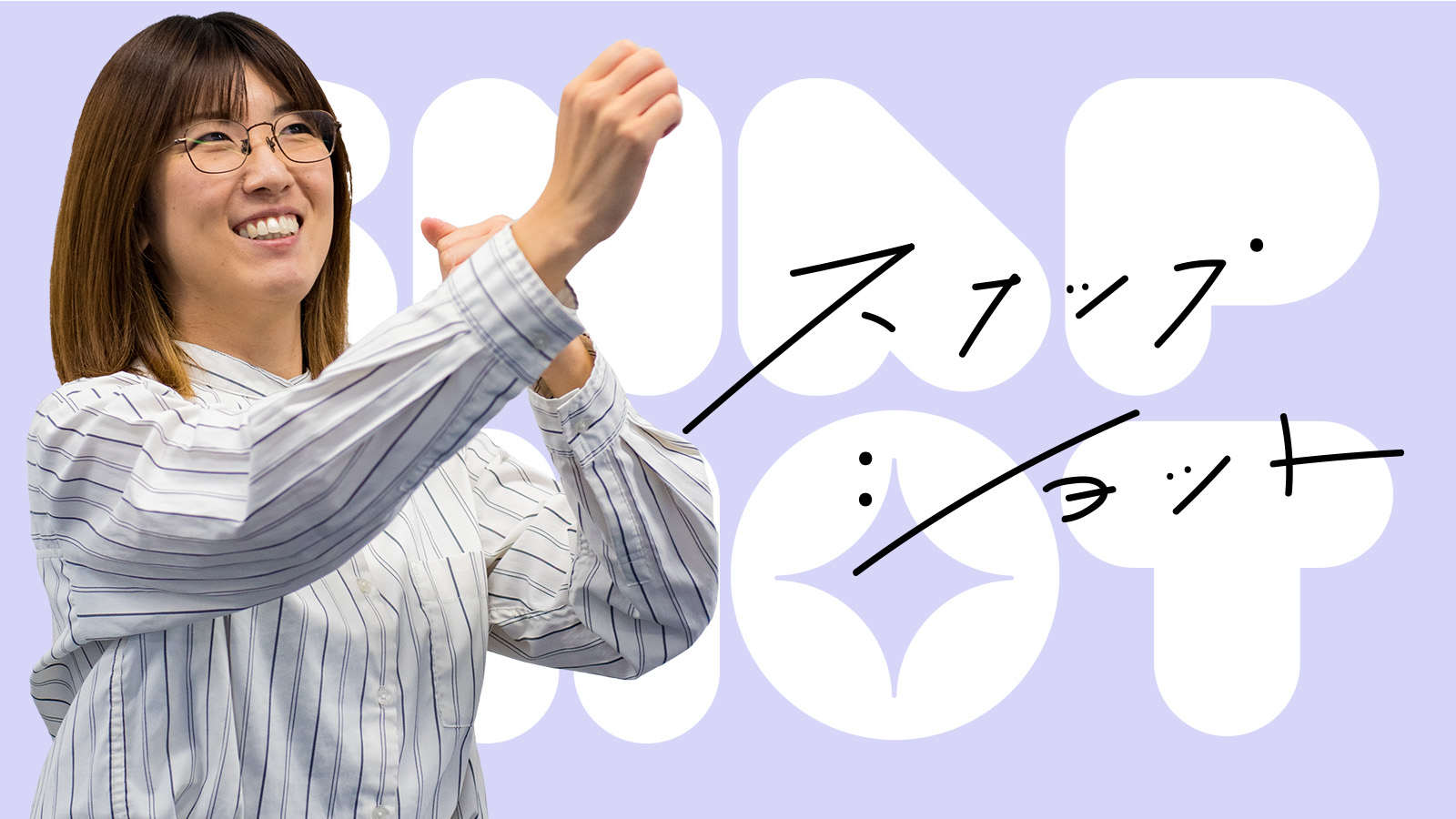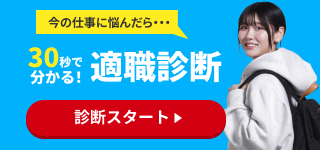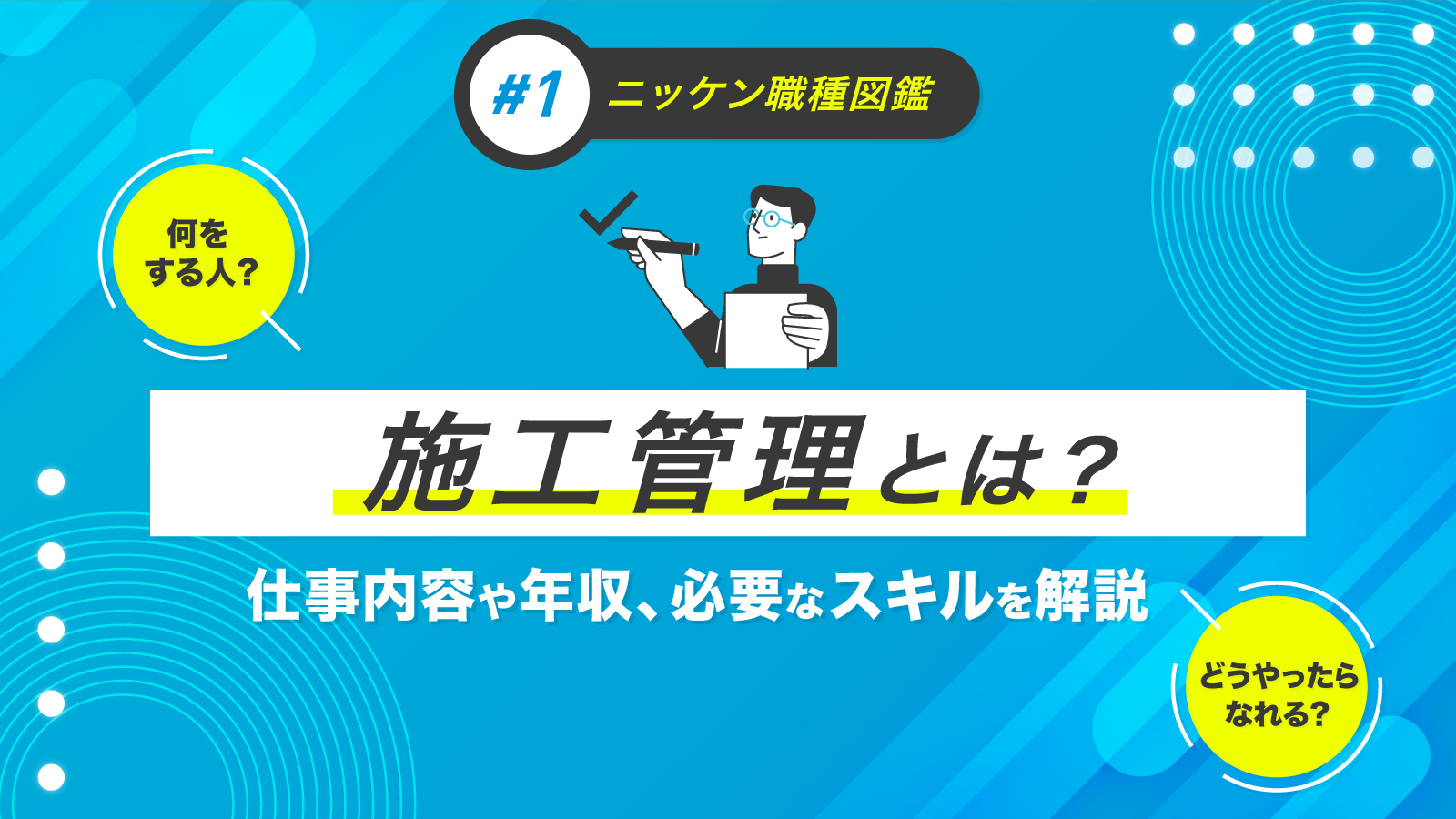
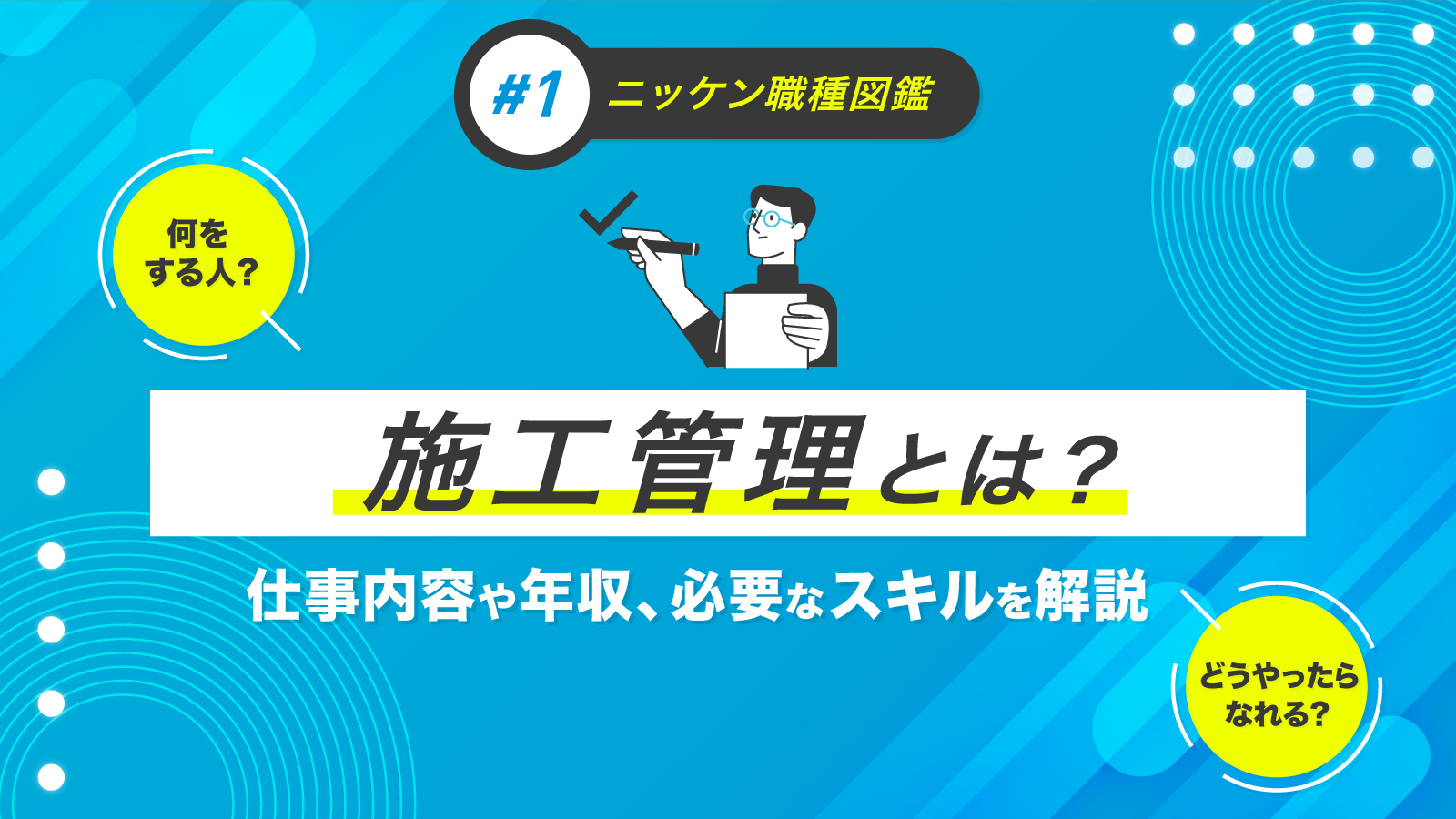
施工管理とは?仕事内容や年収、必要なスキルを解説
2025/03/13
本記事のまとめ
- 施工管理とは、工事が計画どおりに進むように全体を管理する仕事のこと
- 施工管理には工程管理、品質管理、原価管理、安全管理の4つの重要な仕事がある
- 施工管理を含む建設業の平均年収は約547万円
- 施工管理の責任者に必要な資格には、建築施工管理技士や土木施工管理技士、電気工事施工管理技士などがある
- 施工管理のキャリアパスには、資格を取得して現場の責任者になるなどがある
- 施工管理になるには、学校に通って就職する方法や、研修制度がある企業に入社する方法がある
「施工管理とは何をする職業?」と疑問に思う人もいるでしょう。建設現場では、作業員や工事業者など、さまざまな役割の人が関わって工事が進行します。その工事全体のスケジュールを管理し、期限までに工事を完了できるように進めることが施工管理の仕事です。本記事では、施工管理の概要や仕事内容、年収、必要なスキルについて解説します。
本記事を読む所要時間=13分
施工管理とは
施工管理とは、建設工事が計画どおりに進むように現場を統括して管理する仕事のことです。業務範囲は工程管理、作業員の安全管理、建物の品質管理など多岐にわたります。
建設工事には高層ビルやダム、橋など規模の大きなプロジェクトも多く、施工管理者には工事の品質・安全管理をはじめ、行政手続きや竣工時の報告書作成など幅広い専門知識と、作業員など多くの関係者を管理するスキルが求められます。そのため、プロジェクトの責任者になるには国家資格を必要とします。
さまざまな工事現場の経験を積んで資格を取得したり資格レベルを上げたりできれば、手に職がつけられ、収入アップを目指すこともできます。
現場監督との違いは?
施工管理と似た仕事に現場監督がありますが、仕事内容は異なります。
施工管理は建設現場の全体を管理する仕事になるため、現場作業のほかに、事務所で計画書や工程表を作成するなどデスクワークが含まれます。
対して、現場監督は工事現場で作業員に直接指示を出して工事を進めることが主な仕事です。
施工管理が作成した計画書や工程表をもとに、現場監督が工事現場で作業員に指示を出すといった流れで工事が進みます。企業によっては施工管理と現場監督を区別することなく、デスクワークと現場での指示の両方を行うところもあります。
施工管理の仕事内容
工事全体の管理といっても、実際にはさまざまな業務を行います。なかでも、施工管理の仕事として重要なのが工程管理、品質管理、原価管理、安全管理の4つの管理です。
工程管理
工程管理とは、工事が計画どおりに進むように現場を管理することです。工事が着工すると、施工管理者は最初に建物の完成までのスケジュールを定めた工程表を作成します。そして、工程表に沿って、工事に必要な作業員や資材を手配します。
その後、工事の進捗と工程表を毎日見比べ、遅れが発生していれば作業員の人数を増やすなどの措置をとり、工事を順調に進められるように管理します。
また、工事現場では複数の施工業者が同時に作業を行うことが多く、適切なタイミングで必要な工事をそれぞれの施工業者に依頼するために工程管理が必要です。もし工程管理をせずに進行が遅れると、無理なスケジュールで残りの工事を進めなくてはならなくなります。
無理なスケジュールで工事を進めることは、作業員の事故や手抜き工事の原因となるおそれがあるため、工程管理は施工管理者の重要な業務の1つです。
品質管理
品質管理とは、建物の品質を一定に保つために現場を管理することです。建物は設計図をもとに作られるため、施工管理者は「建物が設計図どおりに作られているか」をチェックする必要があります。
施工管理者は、工事が完了したタイミングで品質を確認するための検査を行います。検査に合格すれば、次の工程の工事が始まります。このように特定の工事が終わるたびに検査を実施して、設計図どおりに作られているかをチェックします。
たとえば、完成後に建物の欠陥が見つかった場合、修理に大きな時間と費用がかかります。利用者が安心して建物を使うためにも、また不必要な修理によって利益を下げないためにも、品質管理は重要な仕事です。
原価管理
原価管理とは、建設工事でコストを管理して利益を向上させることです。建設工事では、着工時に全体の予算の中からそれぞれの工事に必要な予算が割り当てられます。施工管理者は予算内に工事が完了できるように施工業者を選定し、作業員や資材を手配します。
それは原価管理を適切に行わないと、予算を超過して赤字工事となってしまう場合があるためです。安価な資材を調達したり、計画より短い工期で工事を進めたりするなど、施工管理者の創意工夫により原価を抑えて利益を上げられるため、腕の見せどころの1つです。
赤字は自社の利益を減らすだけでなく、それぞれの工事に協力してくれた施工業者に必要な金額を支払えなくなる原因になります。工事に関わるすべての企業が利益を上げられるように、しっかり原価管理をすることが大切です。
安全管理
安全管理とは、作業員の安全を守るために建設現場の作業環境を整備する仕事です。建設現場では足場を使った高所作業や、クレーンやバックホーなどの重機を使った作業が行われます。足場に不備があると作業員が落下する危険があり、また重機の配置を間違うと作業員と重機が接触する可能性が発生します。そのため、施工管理者は工事ごとに作業計画を作成し、日々計画どおり作業が進められているかを管理する必要があります。
安全管理をおろそかにすると作業員や近隣住民をケガさせるおそれがあります。そのため、施工管理者には建設工事に関わるすべての人々が安全に作業できるように、徹底した安全管理が求められます。
施工管理に求められるスキル
施工管理には工事を円滑に進め、現場をうまくまとめることが求められます。そのために必要な4つのスキルを紹介します。
コミュニケーション能力
建設工事は発注者をはじめ、設計者や作業員など多くの関係者が交わりながらプロジェクトが進められます。それを管理する施工管理者にとって、それぞれの関係者と意思疎通を図り、必要な情報を共有して工事を進行するコミュニケーション能力は不可欠なスキルです。
工事工程や作業計画は施工管理者が独断で決めるのではなく、それぞれの関係者との話し合いの中で決定します。必要な情報をわかりやすく伝えることに加え、相手が伝えたいことを正確に読みとるための聞く力も問われます。
マネジメント能力
マネジメントとは、企業や組織のリーダーが資源を効率的に活用することをいいます。たとえば、建設工事では必要な場所に、必要なタイミングで、必要な量の人と物を手配しなければいけません。
限られた予算の中で利益を上げるためには、人と物を適切に管理するマネジメント能力は必須スキルです。施工管理者は、現場全体を統括するリーダーとして全体を俯瞰した適切な判断が求められます。
スケジュール管理能力
施工管理者は工事全体のスケジュールを把握し、それぞれの工事が予定どおり進んでいるか管理する能力が求められます。
もし無理のあるスケジュールで工事を進めると、事故が起きるおそれや手抜き工事による品質低下のおそれがあります。建物の完成が遅れた場合、施工者だけでなく発注者にも多大な被害を及ぼします。日々、工事の進捗をチェックし、遅れが出れば適切な措置を取るのが施工管理に求められる責務です。
問題解決能力
建設工事は建築士が作成した 設計図をもとに詳細な施工図を作成して、工事を進めます。建物は一品生産で現場ごとに作り上げるため、図面どおりに工事が進められない状況が発生します。たとえば、天候や地理的な条件によって工程表どおりに工事が進まない場合もあります。施工管理者には、このような突発的な問題に対して自ら進んで解決する能力が求められます。
問題の原因を特定して選択肢を検討し、リスクを洗い出します。関係者の意見を集めた上で対応策を十分に検討したら、最後に決断するのは施工管理の仕事です。そのため、施工管理者には問題から目を背けず、主体的に解決するスキルが求められます。
施工管理に必要な資格
建設工事では現場ごとに監理技術者、主任技術者といった工事の責任者が配置されます。工事の責任者になるには、国が定めた資格を有する必要があります。施工管理が工事の責任者になるためには、担当する工事の種類によって資格を取得しなければなりません。
それぞれの工事に必要な資格について紹介します。
建築施工管理技士
建築施工管理技士は、鉄筋工事や内装工事など建設工事全体を統括する施工管理者に必要な国家資格です。建物の規模により1級、2級にわかれており、都市開発などの大きなプロジェクトの責任者になるには1級建築施工管理技士の資格が必要です。
2021年には、施工管理技士を補佐する施工管理技士補の資格が新設されました。施工管理技士の指導を受けながら管理業務を行い、現場の実務経験を積むことができます。
土木施工管理技士
土木施工管理技士はトンネルやダム、橋などの土木工事の施工管理者に必要な国家資格です。災害復旧やインフラ整備など土木工事全体の責任者として現場を管理します。土木工事施工管理技士は工事の規模により1級と2級にわかれています。空港整備など大規模な土木工事の責任者になるには、1級土木施工管理技士の資格が必要です。
電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、建設工事や土木工事に必要な電気工事の施工管理者に必要な国家資格です。電気工事は鉄筋工事や内装工事といった建築工事と比べて、より専門的な知識や経験が必要です。
電気工事を実施する場合、建築施工管理技士や土木施工管理技士とは別に、電気のスペシャリストである電気工事施工管理技士の資格を持った施工管理者が必要です。建物の電気工事だけでなく、発電所や送電線、電車の架線といったインフラ関係の電気工事も電気工事施工管理技士が責任者になります。
管工事施工管理技士
管工事施工管理技士は建物の給排水設備や空調設備、消火設備などの管工事の施工管理に必要な国家資格です。管工事の責任者となるには、管工事施工管理技士の資格が必要です。
一般的な建物の給排水設備や空調設備だけでなく、工場や発電所などの生産設備を稼働させるプラント工事の施工管理も管工事施工管理技士の仕事です。プラント工事は生産設備ごとに特別な技術で計画・施工しなければならないため、より高い専門性が求められます。
電気通信工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士は、電話やインターネットなどの電気通信工事の施工管理に必要な国家資格です。最近の建物は防犯カメラ・電気錠などのセキュリティ設備をはじめ、同時に空調・照明を一括管理するシステムの導入も増加傾向にあります。建物の情報化技術の導入を受け、電気通信工事の現場を管理する電気通信工事施工管理技士が注目されています。
造園施工管理技士
造園施工管理技士は、緑地・緑化に関する工事全般の施工管理に必要な国家資格です。植栽・庭園などの造園工事だけでなく、公園や広場など緑地・緑化を取り入れたいインフラ関連の施工管理も造園施工管理技士の仕事です。
造園施工管理技士は、すでに整備された施設の除草や剪定など緑の育成管理業務も行います。例えば、国立公園や競技場、ゴルフ場といった施設でも造園施工管理技士が活躍しています。
施工管理が注目される背景と将来性
施工管理は、将来性の高い仕事として注目されています。国内の建設投資は、2008年のリーマンショック後から増加の一途をたどっています。
一般社団法人日本建設業連合会がまとめた統計によると、2010年度に41兆円であった名目建設投資は2024年度には73兆円まで増加しています。東日本大震災などの災害復興や、東京オリンピック・大阪万博などの国際イベント、都心の再開発などにより建設投資は増え続けています。新築工事だけでなく既存建物のメンテナンスのための修繕工事への建設投資も増加傾向にあります。修繕工事の建設投資は2010年度の12兆円から、2024年度の25兆円と投資額は2倍以上に増えています。
国内の建設投資は増加傾向にあるものの、建物を作る働き手の数は不足しています。2010年度に498万人だった建設業の就業者数は、2024年度には483万人に微減しています。就業者の高齢化も進み、29歳以下の就業者数は全産業の平均を大きく下回っています。
増え続ける国内の建設投資に対応すべく、近年建設工事を管理する施工管理者の需要が高まっています。
参考:「建設業デジタルハンドブック 1.建設投資の動向」(一般財団法人建設業連合会/2024年6月更新)
参考:「建設業デジタルハンドブック 4.建設労働」(一般財団法人建設業連合会/2024年5月更新)
施工管理の年収
国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査では、施工管理が含まれる建設業の会社員の平均年収は約547万円でした。会社員全体の平均年収が約460万円と比較し、高い傾向にあります。
理由として考えられるのは、建設工事は現場ごとの一品生産であり、施工管理は多くの人・物を管理・調整しなければならない難しい業務を遂行し、工程・安全・品質面において大きな責任を背負うためです。
建設工事では現場ごとに監理技術者、主任技術者といった施工管理の責任者を配置しなければなりません。責任者になるには国家資格を取得する必要があり、資格取得者は任命されればさらなる年収アップが狙えます。
国内で建設投資が増え続ける中、働き手不足が深刻な建設業においてスキルと経験を生かし、高収入を得られるのが施工管理の大きな魅力といえます。
参考:「令和5年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)
参考:「令和5年分 民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」P153(国税庁)
施工管理のキャリアパス
施工管理のキャリアパスは、次の3つです。
- 資格を取得し現場の責任者になる
- 大手ゼネコンに転職する
- 発注者に転職する
キャリアパスの1つ目は、資格を取得し監理技術者や主任技術者といった現場の責任者になることです。現場の責任者になれば、年収アップが期待できます。経験を積み、大きなプロジェクトの責任者を任されるようになれば、企業内の役職も上がり、さらなる年収アップを狙えます。
2つ目は、大手ゼネコンに転職することです。大手ゼネコンはプロジェクトの規模が大きく、同じ施工管理の仕事をしていても高い年収が期待できます。大手ゼネコンでは住宅やビルだけでなく、空港や駅、工場といった規模の大きなプロジェクトを担当できる可能性が広がります。また、国内だけでなく海外で活躍する機会もあり、スキルや経験をさらに高めることができます。
3つ目は、施工管理の経験を生かして発注者に転職することです。施工管理の知識や経験は、発注者として建物を企画する分野でも生かすことができます。たとえば、不動産ディベロッパーとして都心の再開発を企画したり、機械メーカーの工場の施設管理としてポンプやボイラーなどの設備機器の管理や 新しい生産ラインを企画したりすることもできます。工事現場の施工管理経験は、発注者側でも存分に生かせます。
いずれのキャリアパスも、施工管理として現場を管理するスキルを身につけることが必要です。施工管理技士などの国家資格を取得すれば、知識や経験の裏づけが得られ、キャリアパスを描きやすくなるでしょう。
施工管理になる方法
施工管理には、建築・土木・電気系の高校、大学、専門学校から建設会社に就職する方法が一般的です。専門知識を学んだ学生は入社後に即戦力として、施工管理の仕事を行います。
ほかにも、未経験から施工管理になる方法もあります。建設会社の中には経験不問で施工管理を募集している企業もあります。施工管理のプロ集団を抱える企業では、未経験者を一から教育して現場に配属する仕組みを確立している企業もあります。
日研トータルソーシングも、未経験者が施工管理を学べる研修センターを全国に4か所整備しています。建設業の基礎やパソコンを使ったCAD研修、実際の建設現場を見学して現場感覚を習得するなどの教育を受けることができます。
監修者

藤井 智史
コンストラクション事業部 インストラクター(研修講師)
未経験者に寄り添い、建設業界への第一歩を全力でサポート。信頼と挑戦を大切にした研修を提供します!
プロフィール
2016年から建設業の派遣会社に入社し、施工管理業務を4年弱経験した後、2020年より日研トータルソーシング株式会社に入社。前職と併せて施工管理業務を7年経験し、2022年から研修講師を務める。
現場経験を活かして、施工管理未経験人材研修を実施。
研修を担当した卒業生は600名弱にのぼる。
資格
- 1級施工管理技士
- RSTトレーナー
- 高所作業車運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 第一種衛生管理者
TAG