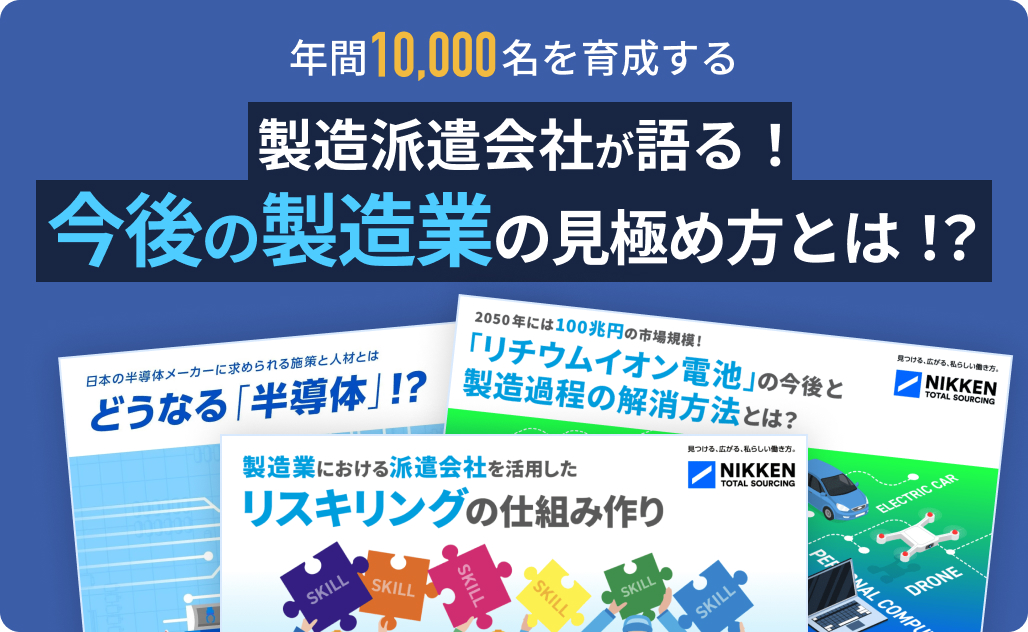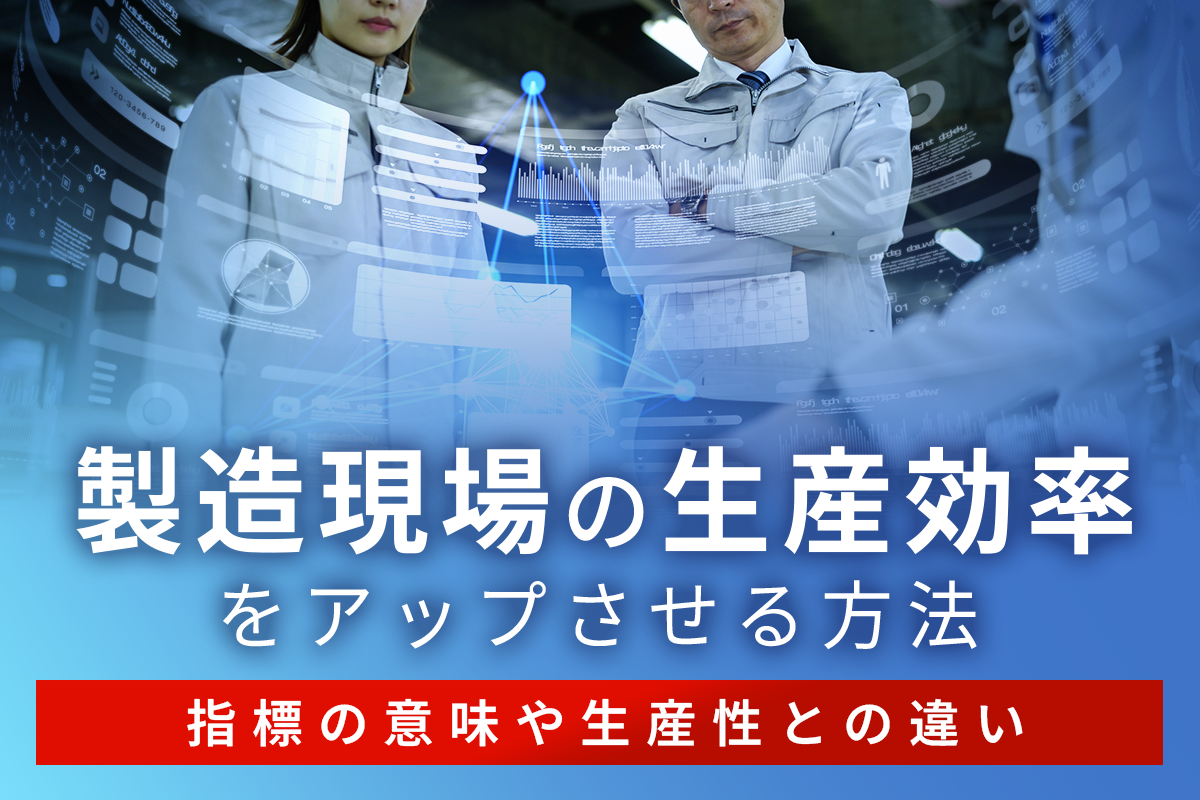
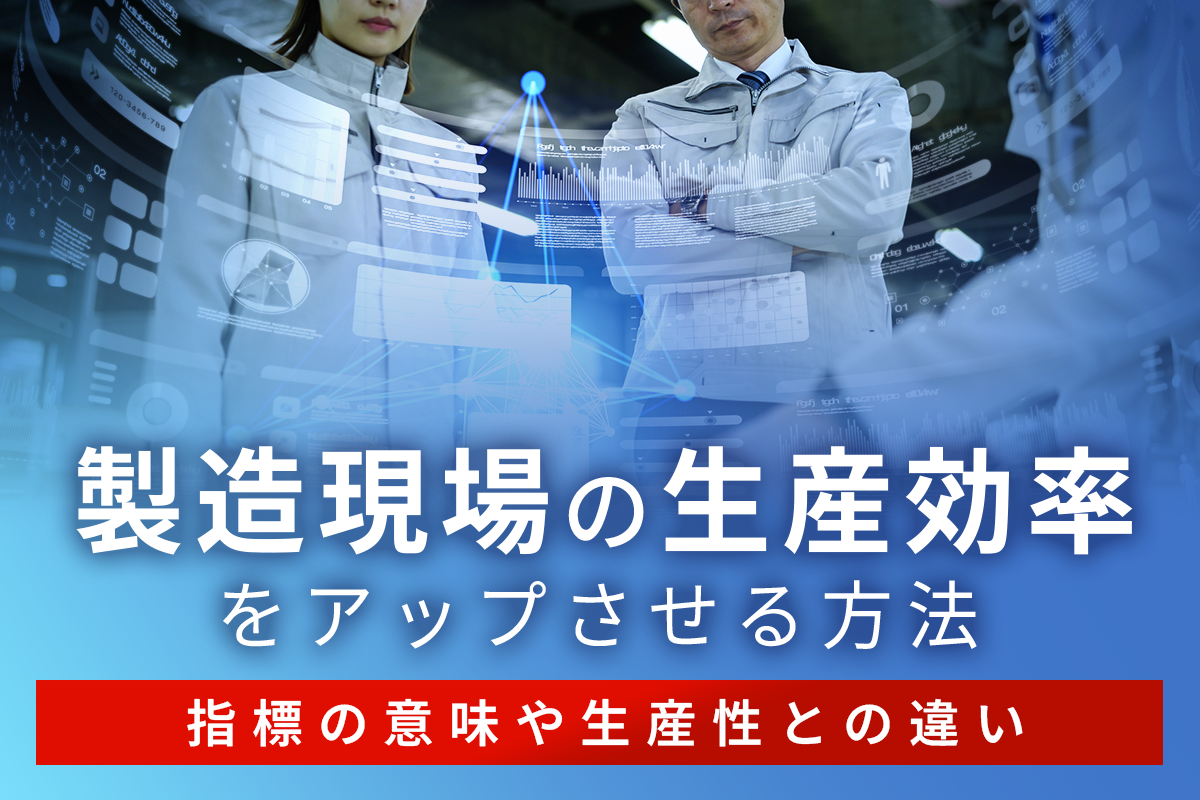

製造業をはじめ、食品や物販など幅広い業種・業態で「トレーサビリティ」の導入が進んでいます。製造事業者にとって、トレーサビリティの確立は製品の品質や生産性の向上に役立つほか、消費者からの信頼獲得の面からも重要なものです。
トレーサビリティとは、製品の生産から消費者に届くまで(あるいは廃棄まで)の一連の工程を記録し、追跡可能な状態にすることを意味します。
また、トレーサビリティは品質管理に欠かせないシステムでもあります。トレーサビリティのシステムを導入する目的やメリット、事例や管理方法などを紹介していきます。

トレーサビリティとは、原料の調達から生産、消費までのサプライチェーン全体の各工程を追跡可能な状態に落とし込むことです。「traceability(トレーサビリティ)」の言葉は英語の「trace(追跡)」「ability(能力)」に由来し、日本語では「追跡可能性」「生産履歴」などと訳されます。
意味の定義は業界によって多少異なりますが、製造業においては原材料や部品の「調達」から、加工や組立などの「生産」、そして「流通」「販売」までの各工程で仕入れ先や製造者を記録して、追跡可能なシステムを構築することをいいます。
いまではトレーサビリティという言葉は、食品や医薬品、自動車、電子部品などの製造業界や販売業界など、幅広い業界で用いられています。なお、日本国内で浸透していくきっかけとなったのは、2003年にアメリカで発生した乳牛のBSE問題と、それによる牛の個体識別番号による管理です。農林水産省は「耳標」というタグを用いて、牛を1頭ごとに固体管理することを法律で義務付けました。
また、トレーサビリティにおいて、時系列を遡って部品や製品の動きを遡及することはトレースバッグ、時系列に沿って追跡することはトレースフォードと呼ばれます。

製造業において、トレーサビリティを確保する主な目的やメリットには以下が挙げられます。
トレーサビリティの導入で、原材料や部品の納入工程、加工などの製造工程、流通に関わる物流工程などの記録が蓄積されていきます。結果、製品の不良や欠陥が判明した際には、各工程の記録をたどり問題の工程を早期に特定。問題を容易に発見でき、問題解決への迅速な着手が可能になります。
問題のある製品の製造番号などを速やかに把握できれば、不良品の回収やリコール対応などをシームレスに進めることができ、時間工数や不良品回収などに関連するコスト低減につながります。問題発生によるリスク・損害を抑えて早期に売上を回復していくなど、リスク管理体制の強化にもつながっていくでしょう。
各工程の記録が蓄積されていくと、問題をはらむ工程や製品不良が起きるボトルネックを特定しやすくなり、それをもとに改善を図っていくことで歩留まり率が向上します。また、製品不良が起きたときの責任の所在が明確になることから、「製品不良を出さない」という現場の意識の高まりも期待できます。
納品先や顧客データの蓄積は、受注予測に活用して生産計画フィードバックする、あるいは顧客に応じたマーケティング施策を展開するなど、顧客管理の効率化に役立てられます。
また、トレーサビリティを構築し原材料の仕入れ先や製造場所などの情報を公表し見える化を図ると、消費者の自社への信頼性が向上します。「どこの国の」「どの工場で」作られたのかわからない製品よりも、「○○から原料を仕入れ」「××工場で製造した」と明確に把握できる製品の方が、消費者にとって安心です。
さらに「安全で安心できる製品を製造する企業」としてのブランドイメージ構築にも寄与します。こうしたトレーサビリティを活用したブランディングは、企業規模に関わらず取り組むことが可能なものです。
トレーサビリティという言葉は、実際にどのような形で使われているのか、例文もとに確認します。
トレーサビリティは「導入する」「とる」「確立する」「確保する」「担保する」「構築する」といった係り受けで使われます。トレーサビリティのシステムをつくるのは「トレーサビリティを構築する」、トレーサビリティのシステムが構築され、情報を共有できる制度ができていることは「トレーサビリティを確保する・確立する」といわれます。

業界によって捉え方などに違いが見られますが、トレーサビリティは構築する範囲によって大まかに「チェーントレーサビリティ」と「内部トレーサビリティ」に分類されます。
チェーントレーサビリティとは、原材料や部品の調達から、加工や組立といった生産、流通、販売まで、サプライチェーン全体の各工程の部品や製品の履歴を把握できる状態にすることです。一般的にトレーサビリティといわれるのは、こちらのチェーントレーサビリティを指し、構築にあたっては各段階に関わる企業間の連携が不可欠になります。
製造事業者は、製造した製品がどこに行ったのかの追跡や、原材料や部品がどこから来たのかの遡及が可能になります。製品の不具合や故障が判明したときに原因を究明しやすくなるほか、製品の回収にも迅速に着手できるようになることがメリットに挙げられるでしょう。
消費者にとっても、どのような事業者を経て手元に届いたのか正確に把握できるようになり、安心感を獲得できるメリットがあります。生産地や製造地の偽装の抑止力にもなることも安心材料です。
内部トレーサビリティとは、サプライチェーンに含まれる特定の企業や工場、物流拠点といった範囲に限定し、部品や製品の移動を把握できる状態にすることです。パソコンを製造する工場を例に挙げると、各部品の仕入先、組立方法などの作業方法、検査内容、完成した製品の納入先などを追跡できる状態です。
内部トレーサビリティの構築は、業務効率化や品質の安定化に役立ちます。
製造業で内部トレーサビリティを構築するにあたって、履歴を記録していく過程は多岐にわたります。原材料や部品の入荷から製品の出荷に至るまで、各工程で部品や製品、あるいはロット単位で識別記号を付与し、作業内容や寸法情報、検査内容などを記録していくプロセスです。
また、工具や治具など繰り返し使用される道具の管理・運用にも、内部トレーサビリティが用いられています。
工具や治具の一本一本にレーザーマーカーで識別番号を印字し、工場や保存場所の棚番号といった情報を付与して、マスタ登録を行っておきます。そして払出や返却の都度、バーコードリーダーで読み取って記録します。
これにより、工具や治具の使用者を管理できるだけではなく、使用回数なども把握できるため、研磨するタイミングや廃棄するタイミングを見極めることで、製品の品質の安定化に役立ちます。
トレーサビリティはサプライチェーンの各工程に分散されているデータを収集して、全体の状況を把握するものです。正しい情報を連結して共有していくには、データの改ざんや不正な閲覧を防止し、データの信頼性や安全性を担保する技術が前提になるでしょう。
そこで注目されているのが、暗号資産(仮想通貨)などにも活用されている技術であるブロックチェーンです。ブロックチェーンは、特殊な記録帳をサプライチェーン全体で共有し、それぞれのデータは前の過程のデータと連結されている仕様となっているため、改ざんを行うのは困難です。トレーサビリティにブロックチェーンの技術を導入することで、高い機密性を確保するとともに、迅速な記録を実行できるようになります。

トレーサビリティの構築は、製造業DXに関連するオペレーションです。トレーサビリティの管理方法や製造業DX、スマートファクトリーとの関連について確認します。
製造業におけるトレーサビリティ管理には、識別番号の付与にバーコードや2次元コードを用いるのが一般的です。各工程でバーコードや2次元コードを読み取り、作業内容や検査内容、検査画像などを記録して、後工程で活用していきます。
従来はラベルプリンターを用いて、バーコードや2次元コード、品名や製造日などの情報を印字し、部品や仕掛品、製品に貼付して管理を行っていましたが、近年ではレーザーマーカーが使用されています。
レーザーマーカーは、レーザーを発光させて、部品などに文字やバーコード、2次元コードなどを発色、あるいは刻印して付与する機器です。凹凸面にも印字が可能で、ラベルプリンターと比較してインクなどの消耗品を交換する必要がないといったメリットがあります。
また、各工程ではバーコードリーダーなどで識別番号を読み取り、記録を行っていきます。電波を用いてRFタグの情報を読み取るRFIDを導入し、非接触で複数の情報を一度に読み取るなど、オペレーションの効率化も進んでいます。
製造業DXとは、モノづくりの現場で培ってきた属人的なノウハウを、デジタルの活用でデータ化し、ビジネスモデルを変革していくことをいいます。そしてスマートファクトリーとは、デジタルデータの活用で業務プロセスを改革し、業務効率化による生産性向上や高品質化を継続して推進していく工場のことです。
つまり、製造業DXを推進してPDCAサイクルをまわしていくことが、スマートファクトリー化につながっていきます。
製造業DXを進めるには、製造工程から出荷、流通、販売、そして保守までのデータを収集して一元管理し、見える化を図るアクションが欠かせません。そして顕在化した課題を解決するためのITシステムを構築し、製品の品質や生産性の向上を実現していくという流れになります。
そのため、トレーサビリティの確保は製造業DXによるスマートファクトリー化の推進に欠かせない施策のひとつに位置付けられます。
製造業DXの概要や事例については、以下の記事で詳しく解説しています。
グローバル化などによる競争の激化も影響し、製造業ではコスト削減や納期短縮、品質の安定化などを図るため、トレーサビリティ確立の重要性がさらに強まっています。「安心・安全な製品を提供する企業」としてのブラインドイメージにも寄与し、消費者からの信頼獲得にもつながっていくでしょう。
お役立ち資料はこちら
半導体・電池業界の研修実績年間10,000名を超える派遣会社が「今後の製造現場を左右する情報」をまとめた資料セットを作成しました。