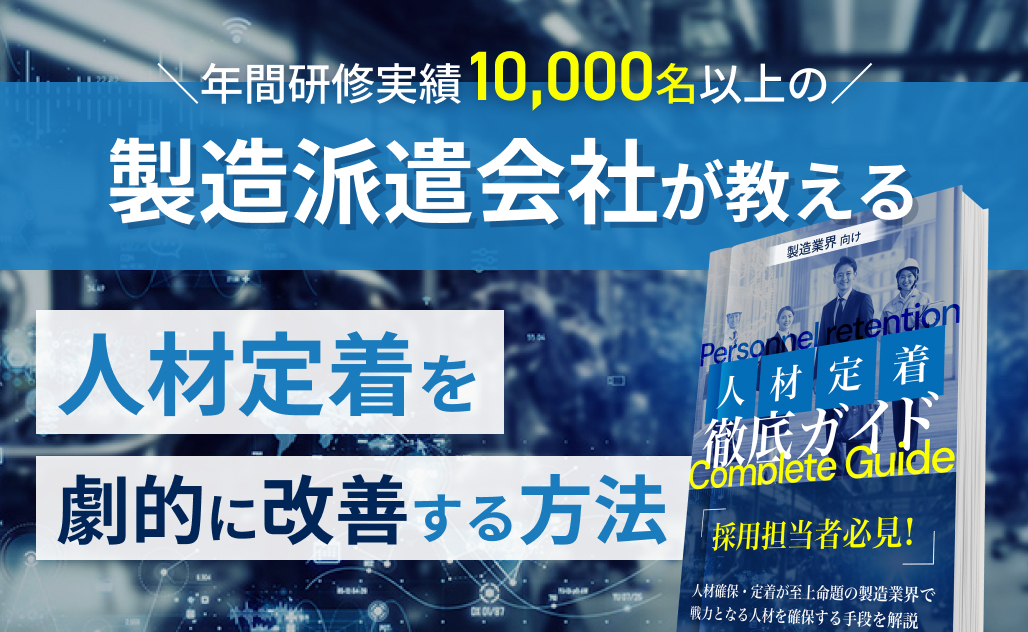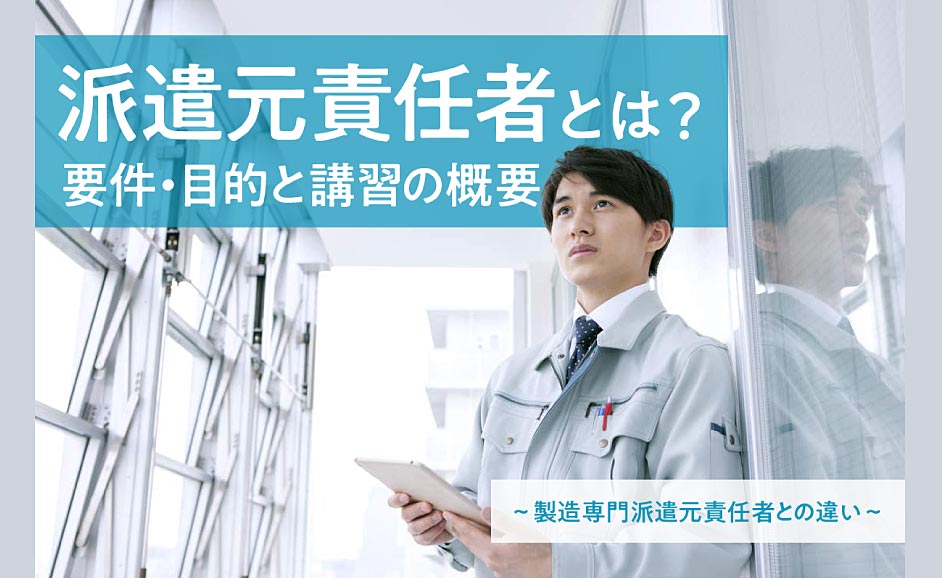
労働者派遣法では、労働者派遣事業者に対して、登録者の雇用管理や保護を担う専任の「派遣元責任者」を選任することが義務付けられています。また、製造業務への派遣においては、製造専門派遣元責任者の選任が義務付けられているという特徴もあります。
こちらでは、派遣元責任者の要件と派遣元責任者講習について、さらに製造専門派遣元責任者との違いについても取り上げていきます。
お役立ち資料はこちら
派遣元責任者とは、労働者派遣事業者(いわゆる派遣会社)に選任された、派遣登録労働者の適切な雇用管理や保護を担う人をいいます。これは労働者派遣法で定められたもので、派遣労働者100人に対して1人以上の派遣元責任者を選任することが義務付けられています。
派遣元責任者には、選任にあたっての要件があります。
<派遣元責任者の主な要件>
このうち特に重要なのは、一定の雇用管理などの経験、そして派遣元責任者講習の受講です。
一定の雇用管理などの経験として認められるのは、成年になって以降の以下の経験です。
なお、派遣元責任者は自社の役員や従業員の中から選任することが義務付けられていて、他社の派遣元責任者と兼任することはできません。さらに、派遣元責任者は派遣労働者にはなれない点にも注意が必要です。
派遣元責任者の職務には、次の項目が該当します。

派遣元責任者講習とは、労働者派遣法による派遣元責任者の選任要件で、受講が義務付けられている講習です。派遣元責任者になるには、派遣元責任者講習を3年以内に受講していることが要件のひとつとなっています。
派遣元責任者講習は1日で行われます。複数の講習機関が実施してますが、講習内容は厚生労働省が策定したものに準拠するため、主催団体による違いはありません。
派遣元責任者講習は、派遣元事業所の雇用管理や事業運営の適正化に役立てることを目的としており、労働者派遣法の趣旨や派遣元責任者の職務、事務手続きなどに関する講習が行われます。
講習の対象となるのは、派遣元責任者に選任されている人や選任される予定の人です。
なお、派遣元責任者には選任要件が設けられていますが、派遣元責任者講習の受講要件はありません。労働者派遣事業に関する知識の習得を図りたい人も受講可能です。
派遣元責任者講習の申し込みは、直接、各講習機関のホームページから行います。派遣元責任者講習は東京や大阪、名古屋のほか、札幌、仙台、広島、岡山、福岡など各地で実施されており、派遣元事業所の住所地を問わず、いずれの講習機関・会場でも受講可能です。
なお、東京では月に20回~30回前後(同日開催を含む)実施されています。
参考:厚生労働省「派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について」
製造専門派遣元責任者とは、労働者派遣元事業者が派遣労働者を製造業務に派遣する場合に選任が義務付けられている、専門の派遣元責任者です。
ここまで見てきたように、派遣労働者の雇用管理や保護を行うため、労働者派遣事業者が派遣元責任者を選任することは、労働者派遣法で義務付けられています。
これに対して、製造業務では危険な機械を操作したり、有害物質を取り扱ったりすることがあることから、派遣元責任者とは別に、製造業務専門の責任者として専任が義務付けられているのが、製造専門派遣元責任者です。
製造専門派遣元責任者は、製造業務に従事する派遣労働者100人に対して1人以上選任することが義務付けられています。製造業務に従事する派遣労働者が100人を超えて200人以下の場合は、製造専門派遣元責任者は2人必要となり、以降100人を超えるごとに1人以上を追加していく形です。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、派遣元責任者を兼任することが可能です。
<必要な製造専門派遣元責任者の人数の例>
労働者派遣法にもとづいて適切に運用されるよう、派遣先企業と労働者派遣元事業者で確認することが大切です。
労働者派遣法では、労働者派遣が適切に運用されるようにさまざまな規定が設けられています。派遣元責任者や製造専門派遣元責任者の選任も、そうした法律による施策のひとつです。
危険な機械の取り扱いなども発生する製造業務の派遣では、製造専門派遣元責任者の選任が義務付けられています。派遣労働者を製造業務に活用する際には、労働者派遣法にもとづいて適切な運用を行う派遣会社を見極め相談しましょう。
年間研修実績10,000名を超える弊社が半導体・自動車業界の企業様から特に好評をいただいた「人材定着」に関する資料セットを作成しました。