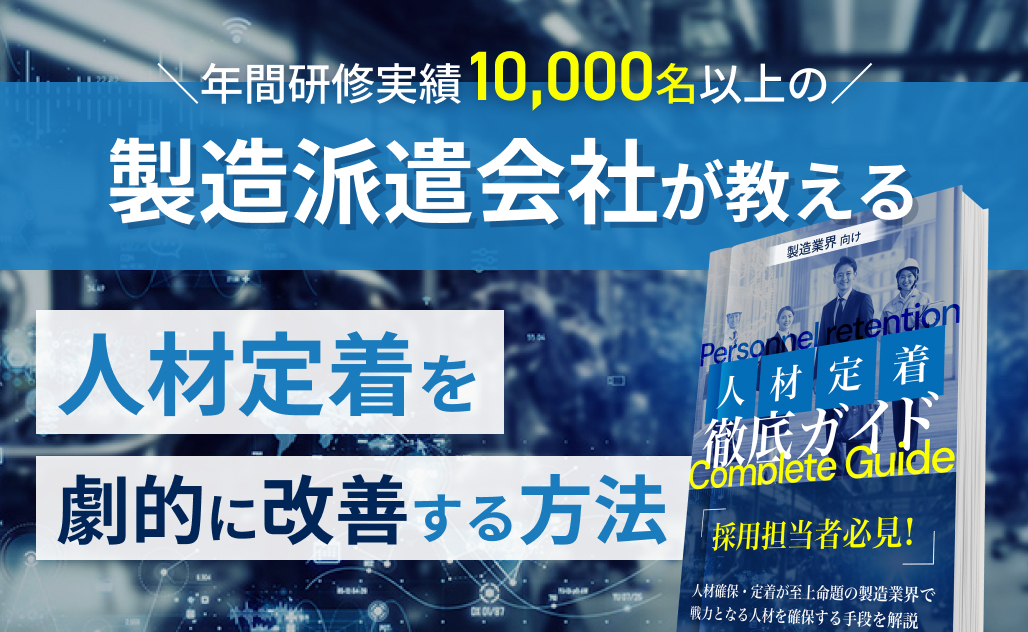工場の機械や設備は適切な維持管理を行わなければ、不具合や故障が生じてしまう懸念が高まり、さらには生産ラインを止めざるを得なくなるといったリスクにもつながりかねません。
そこで、安全に正常な状態で生産設備を稼働させるために、必要となるのが設備保全です。こちらでは設備保全の概要を解説したうえで、設備保全計画の重要性や昨今の課題についても触れていきます。
お役立ち資料はこちら
設備保全とは、工場の機械や設備が安全に、安定的に稼働するように、維持管理を行うことを意味します。設備保全は、事後保全と予防保全に分けられるほか、予知保全という種類もあります。
事後保全とは、設備が故障したときに、原因を調査して対策を講じることを指します。
事後保全の対象となる故障には、機能停止型故障と機能低下型故障があります。
予防保全とは、保全計画をもとに機械や設備の点検や修理、部品交換を定期的に行うことをいいます。事後保全は故障の修理を目的に行うのに対して、予防保全は故障の予防を目的としているのが異なる点です。
予防保全による部品交換には、時間基準保全と状態基準保全という種類があります。
予知保全は機械や設備の故障の兆候を検知して、保全を行うことです。予防保全と予知保全は故障を防ぐために事前に保全を行うという点では同じですが、予防保全は一定の間隔で時間を基準に定期的に保全を行うのに対して、予知保全は故障の兆候があるとき保全を実施するという点で異なります。
予知保全を行うには機械や設備の監視システムが必要であり、近年、IoTの活用が進んだことで、注目されている保全の方法です。
保全と似た意味を持つ言葉にメンテナンスがありますが、定期的に機械や設備の点検や修理を行うという意味では同じです。ただし、保全は機械や設備の安全を守ることを目的としているのに対して、メンテナンスは正常な状態に保つことを目的としているという違いがあります。
設備保全を計画する上で知っておきたい手法に「TPM(Total Productive Maintenance:全員参加の生産保全)」というものがあります。保全担当者だけでなく、トップの経営者から作業員に至るまでが設備管理を行っていくことで、設備効率を最高にするという手法です。
設備管理台帳とは、機械や設備の稼働を開始した日、故障などのトラブルや修理の履歴、メンテナンス状況などの管理のために必要になるものです。主な記載項目は以下になります。

設備保全の適切な実施は、工場の機械や設備の故障を未然に防ぎ、安定稼働と品質確保に不可欠です。また、設備の老朽化が招く事故による労働災害の防止にもつながります。
こうした設備保全の意義は、製造業の経営課題の解決にも直結する、非常に重要な位置づけと考えられます。
製造業における経営課題の主なものとして、「生産コスト」と「労働安全」が挙げられます。
工場の機械や設備の故障は、生産コストのアップや事故による労働災害の発生の要因になるものです。そこで、予防保全と事後保全による適切な設備保全を行うことで、こうした経営課題の解決につながっていきます。
工場の機械などの生産設備の故障によって、能力を十分に発揮できない事態に陥ると、製品不良の発生や生産計画の遅れにつながります。故障の状況によっては、生産ラインを停止せざるを得ないこともあり、その結果、製品不良の分を再度、生産するための原材料費や光熱費などのコストや従業員の残業代などの人件費といった、生産コストの増大を招きます。
こうした設備の故障による生産コストのアップを防ぐには、予防保全を行うのが効果的です。また、故障した機械や設備は修理を行うだけではなく、事後保全を実施することで、再発の防止が期待できます。
予防保全と事後保全を併せて行うことで、生産ラインの安定した稼働と品質の安定につながり、想定外の生産コストの発生を抑えられます。
工場の生産設備が老朽化すると、腐食や劣化による故障が原因で事故が起こり、労働災害につながるリスクが高まります。設備の老朽化に起因する労働災害を防ぐためには、予防保全による維持管理を行い、適切な時期に設備の更新を図ることが大切です。

生産設備の高度化や納期の短期化など環境の変化により、設備保全はよりいっそうの高度化や効率化が求められています。また、適切な維持管理が行われていないことによって事故が発生していることも、目を向けるべき課題となっています。
製造業では、生産年齢人口の減少による人手不足の解消や、グローバル化が進む中で競争力の強化を図るため、生産の省人化による効率化が進められています。
生産設備はオートメーション化が進んだことで複雑化したことから、設備保全に必要とされる知識や技術が高度化しました。また、短納期を求める顧客ニーズによって、製造のリードタイムが著しく短縮化しているため、以前よりも設備の故障が生産計画に甚大な影響を与えるようになりました。
そのため、設備保全を効率よく行い、生産設備を安定して稼働させる重要性が以前よりも高まっているのです。
設備の事故の要因は老朽化だけではなく、人的要因も目立ちます。
消防庁が発表する「令和元年中の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要」によると、特定事業所の一般事故の発生要因は人的要因が全体の38%を占めており、13%は維持管理の不十分が要因です。設備保全を適切に実施できていないことが課題として浮き彫りとなっています。
出典:総務省・消防庁「令和元年中の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要」
人的要因による事故を防ぐべく、設備保全に関わる人材の育成が求められています。生産設備が高度化していることからも、専門性のある人材の育成が急務となっているのです。
設備保全に関する公的な資格には、電気工事士や機械保全技能士が挙げられます。機械保全技能士は、資格の取得のための勉強を通じて、設備保全の業務に必要な知識を体系的に身に付けられる点がメリットです。
生産設備の高度化が進み、製造のリードタイムが短縮している昨今では、適切に設備保全を行い、生産ラインを正常に稼働させることがこれまで以上に求められています。設備保全の専門的な知識や技術を持つ人材の確保は急務といえるでしょう。
なお、弊社テクノセンターでも、機械保全技能士の2級相当の知識や経験を習得できる保全に関する研修を実施し、人材確保のサポートを承っております。
お役立ち資料はこちら
年間研修実績10,000名を超える弊社が半導体・自動車業界の企業様から特に好評をいただいた「人材定着」に関する資料セットを作成しました。